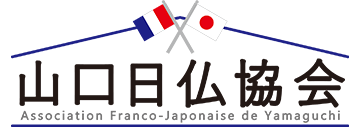ジャン・ペロル『その夏は忘れない』刊行記念
末松壽 講演会 報告
津田義昭
山口日仏協会の初代会長を長年に渡って務められた末松壽先生が、昨年9月に、現代フランスの詩人・小説家であるジャン・ぺロルの小説『その夏は忘れない』を翻訳され、水声社から出版されたが、その刊行を記念して、「ぺロルの小説における詩について」と題された末松先生の講演会が、協会と「文芸山口」の共同主催で、4月29日に、山口市の大殿地域交流センターで、開催された。
 ぺロルは1932年生まれ、青年期の1960年代から日本に長く滞在して、九州大学で教鞭を取り、また東京と九州の日仏学院の院長を歴任し、末松先生とは親交もあるとのことで、日本とは縁が深い人だが、これまでわが国ではあまり知られていないのではなかろうか(早くに、詩集の邦訳は、出ているようだが)。もちろん私も、このたびの翻訳書によって、はじめて、その名を教えられた次第である。
ぺロルは1932年生まれ、青年期の1960年代から日本に長く滞在して、九州大学で教鞭を取り、また東京と九州の日仏学院の院長を歴任し、末松先生とは親交もあるとのことで、日本とは縁が深い人だが、これまでわが国ではあまり知られていないのではなかろうか(早くに、詩集の邦訳は、出ているようだが)。もちろん私も、このたびの翻訳書によって、はじめて、その名を教えられた次第である。
第二次世界大戦では、フランスは、1940年春のドイツの侵攻に壊滅して降伏し、最終的に大戦が連合国側の勝利によって終わるまでの4年間、ナチス・ドイツによる支配の下にあった。
ぺロルの「自伝的」小説3部作の第1作ともいうべき、『その夏は忘れない』(1998)は、南仏の都市リヨンに住む、作者とほぼ同世代の少年ジャノの目を通して、占領期の後半(43年初めの冬)から、戦後1年(45年の夏の終わり)までの時代が、描かれている。リヨンは、パリのような独軍の直接占領ではなく、フランス自らの政府が統治するゾーン(もちろん親独政権ではあるが)に属していたのだが、戦局が次第に枢軸国側に不利になるにつれて、ドイツは圧迫を強め、遂にフランス全土の占領に至った。そういう、暗い季節から、解放を経て、戦争は終わっても、未だ傷は癒えない時期に至る、約2年半である。
 藤川協会長も挨拶で触れられたように、現今の情勢は、この小説に、思いがけないアクチャリティを帯びさせることになったが、しかし、今回の講演で、末松先生が焦点を当てられたのは、直接に「軍事的、政治的、社会的」状況に対してではない。
藤川協会長も挨拶で触れられたように、現今の情勢は、この小説に、思いがけないアクチャリティを帯びさせることになったが、しかし、今回の講演で、末松先生が焦点を当てられたのは、直接に「軍事的、政治的、社会的」状況に対してではない。
私の、小説の初読の印象では、主人公の道程が、「詩人の誕生」という方向に、ちと整序され過ぎているのでないかという感も無くはなかったが、先生の読みでは、むしろそこにこそ、この小説の眼目があるので、ジャノが詩に招かれ、詩への関心を強めていくことが、現実を見る力を深めていく(またその逆の、現実から詩へのアフェクトもある)過程を、つぶさに説明された。
講演の後半は、詩と現実を架橋する方法論として、「詩学」ということを、言われた。「詩学」とは、詩の技術を教える「詩法」でもなく、雑多な知識の集積である「文学史」でもなく、あくまで詩の文学性を対象とするものである、とのこと。
 ぺロルの詩論には、学術性・大系性が欠如しているので、詩学ではないが、実作者であることから、「詩学問題への接近の示唆を受け取ることが出来よう」と、論じられた。先生の該博な知識に、色々「考えるヒント」をいただき、刺激を受けた講演であった。
ぺロルの詩論には、学術性・大系性が欠如しているので、詩学ではないが、実作者であることから、「詩学問題への接近の示唆を受け取ることが出来よう」と、論じられた。先生の該博な知識に、色々「考えるヒント」をいただき、刺激を受けた講演であった。
終演にあたっては、「文芸山口」代表の浜崎勢津子さんから、先生が、この素晴らしい小説を訳されたことにたいして、感謝の気持ちを述べられた、挨拶があった。
コロナ渦の中で、両団体による共同開催に尽力され、実現にこぎつけられた方々のご努力を多としたい。